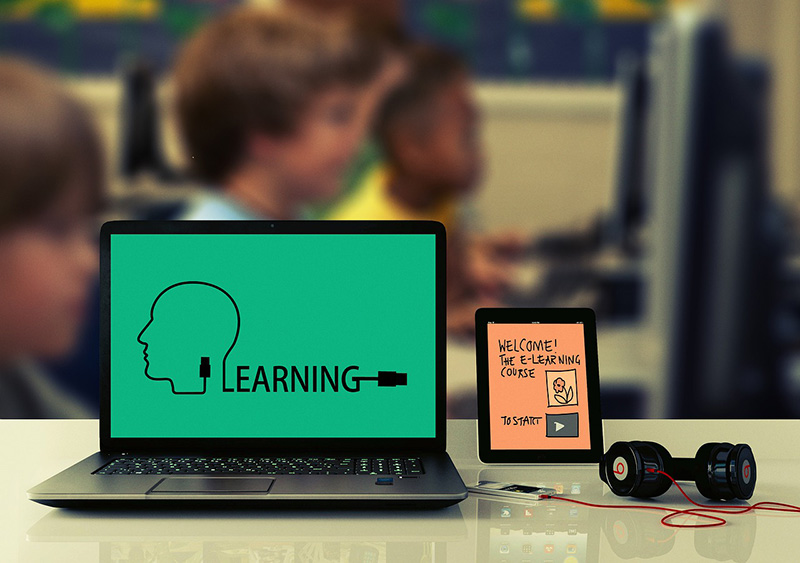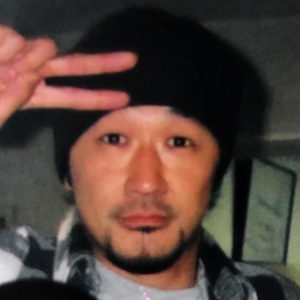
2017年に文部科学省から公示された小学生の学習指導要領にあるプログラミング必修化ですが、勘違いしやすい点もふくめて超簡単にかみくだいて、サクッとわかりやすく説明したいと思います。
だいたい3分くらいで読めます。
[toc]
2020年からはじまる小学生のプログラミング必修化とは
文科省の『学習指導要領』とは、子どもが日本全国どの学校にいてもおなじ内容の授業がうけられるように、文科省が基準となるカリキュラムを示したものです。
その中身に「プログラミングの必修」が記されているわけですが、なぜそれをやるのか・どうやるのかがイマイチわかりにくいですよね。
プログラミング必修化と教育のねらい
大きくわけて次の4つが、小学生のプログラミングを必修とした文科省のねらいだと思います。
- 早いうちから情報モラルの意識と情報活用方法を学ぶ。
SNSでの情報発信もモラルを持って、よくあるバイトテロのような問題を起こさないように、情報の取り扱いかたを教育するもの。 - パソコンやタブレットの役割や使い方になじんでおく。
パソコンやタブレットなどの情報通信機器の役割や、それらをつかってどんなことができるかを理解させるもの。実際にはICT(情報通信技術)で授業するといっても、ほとんどの小学校ではパソコンやタブレットなどの機器の数は足りていないので「さわって覚える」のは学校の授業ではむずかしいです。ただ、たいていの親はスマホを持っていますしパソコンがある家も少なくないので折にふれて子どもたちも馴染んでいるとおもいます。
そういった意味では取り扱いを学ぶというよりも、ICTをどう活用してどんな結果を得られるのかをさらっと算数や理科などの授業のなかで勉強することになるんだろうと思います。
参考までに大阪市立矢田小学校がこちらのWebサイトで活用事例を紹介しています。 - 「アダプティブ・ラーニング」で一人ひとりの理解度に合わせた学習を可能にする。
最近ニュースにもなる親からの暴力など家庭で生じる問題があります。学校生活や学習だけでなく、そうした生活指導も含めてきめ細かな対応ができるようにする環境を整えようという考えです。 - プログラムを作るときの考え方である論理的思考を学ぶ。
あとですこし詳しく説明しますが、プログラムを作るときに命令を組み立てていく考え方をまなぼうということです。
『プログラムを作る』ような新しい授業ができるわけではない
『プログラミング必修化』といきなり言われたら勘違いしてしまうのが次の3つです。
- 授業が増えるの?
- プログラマーになる勉強?
- パソコンを使って授業するの?
授業は増えない
必修とはいえ『プログラミング』という授業、科目が増えるわけじゃないです。
「今日の4時間目は『プログラミング』です」ということにはなりません。
プログラマーを養成するわけではない
『〇〇言語』といった、いわゆる『プログラミング言語』をおぼえさせて将来のプログラマーを育成するわけじゃないです。
ICT(パソコンやタブレット)は必ずしも使わない
文部科学省の平成28年10月の資料によれば、平成28年3月の時点で学校の教育用コンピュータ1台に対して6.2人(目標は3.6人)です。
つまり“ひとり一台”にはかなり遠い。
なので実際には「アダプティブラーニング」も現時点では実現はむずかしい状況だと思います。
『論理的思考力』って何?
説明するまでもないですが、さっきから出てくる「論理的思考」とは、以前に流行ったいわゆる『ロジカルシンキング』です。
論理とは
じゃ、論理って何?ってことですけどこんな感じ。
論理とは、一見なんの関連もなさそうな事象であってもその関係性をさぐって法則性を見つけ出し、将来の予測を立ててみたりすることです。
そして論理的思考はその方法をつかう考え方。
そうしたいわゆるロジカルシンキングを小学生のうちから養うのはとてもたくさんのメリットがあります。
論理的思考力を持つとどうメリットがあるか?
論理的思考力が身につくと、物事を俯瞰したり客観的にながめる、あるいは精度のたかい見通しをたてたり、すぐれた判断力をもつことができるようになります。
行動が一つひとつ整理されるのでムダがなく、誰かがひとつチャレンジしている間に二つ三つとチャレンジする機会を得ることができます。
つまり将来的に成功する確度があがる。
起業家の人が話がわかりやすかったり、たて続けに成功するのはこのためだと思ってます。
また、子どものころからこの訓練がなされると大人になってからの苦労がひとつ減ります。
仕事でのコミュニケーション能力が圧倒的にあがるからです。
例えば仕事でだれかと打ち合わせするとき、これから話すことについて相手がどの程度のことを知っていて、それを前提にどこから話し始めれば良いか、どこまで話せばいいのかなどを考えるクセがつくので会話にメリハリもでて仕事もスムーズになります。
論理的思考力がないと「彼の言うことはさっぱりわからん」ということになります。
プログラミングもそうですが、世にあふれるデザインされた印刷物やWebサイト、マーケティングの仕事などは、この論理的思考力によって“出来栄え”や“結果”が大きく変わってきます。
まとめ
ICTの普及が進んでいないことを含めて考えてみるとプログラミングの必修化うんぬんというよりは、やはり「論理的思考力を養う」ことが現実的かなと思います。
プログラミング方式で勉強しなくても、個人的には「フェルミ推定」を小学生でもチャレンジできそうな簡単なテーマにしてやったら、相当たのしい授業ができると思います。
『プログラミング学習』という言葉だと、多くの人が勘違いするのは当たり前かと思いますので。
指導要領よりも文部科学省と総務省、経済産業省が連携・運営するWebサイト『未来の学びコンソーシアム』をみると、国が考えているミッションがよくわかります。
『プログラミング必修!』と言われて驚いたのは学校の先生たちも同様でしょう。そのために3省庁が連携して『未来の学びコンソーシアム』を立ちあげたようです。
これはそもそもプログラマーではない教師たちがどのようにして授業に取り組めばいいかの指針が書かれているので、自分のお子さんが学校でどういう教育を受けさせれるのかをより深く理解したい方は一読されるといいかもしれません。
お父さんお母さんも論理的思考力を身につけると家での会話も論理的になって、お子さんの成績もあがるかも。
ちょっと古い本ですが『地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」』がおすすめです。